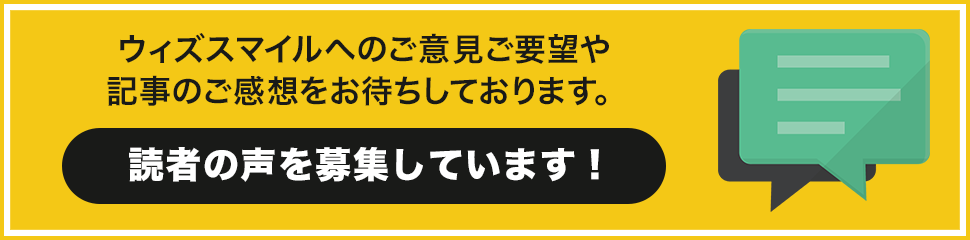くらしの役立ち情報
2024.10.25
蓄電池の使い方から有用性を知ろう!目的別・モード別ごとに紹介
 (1).jpg)
電気代の高騰や環境配慮への対応が求められるなか、家庭用の蓄電池に注目が集まっています。蓄電池は電気を貯めておける便利な設備ですが、具体的な使い方や効果的な活用方法について、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、蓄電池の基本的な使い方をはじめ、目的別・モード別の活用方法、最適な蓄電池の選び方までをわかりやすく解説します。蓄電池の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは、蓄電池の使い方を操作面と目的別に分けて見ていきましょう。
蓄電池の導入後は、特定のモードに設定して使用するのが基本です。各モードの詳細は、のちほど「蓄電池のモード別の使い方」で詳しく説明します。
通常、蓄電池のモードが自動で切り替わることはありません。このため、使用目的や状況に応じて手動でモード変更が必要です。
ただし、停電時には自動で自立運転モードへ切り替わるタイプの蓄電池もあります。自動でない場合、停電時には手動で自立運転モードに切り替えないと、蓄電池から電気を供給できなくなる点に注意しましょう。
すでに蓄電池を導入している、あるいは今後導入を考えているという方は、手動・自動のどちらで自立運転モードに切り替わるタイプなのかを確認しておくと、もしもの停電時にも安心です。
蓄電池の操作方法や機能は、使っている機器の取扱説明書もしくはメーカーの公式ホームページからチェックできます。
蓄電池単体で導入する目的は、「電気代の節約」「停電時などの災害に備えるため」の2つが挙げられます。
電気代の節約を目的として日常的に使用する場合、電気代の安い時間帯(主に深夜)に電力会社から電気を購入し、蓄電池に貯めます。蓄電しておいたぶんを電気代の高い時間帯(主に日中)に使うことで、電気の購入費用を抑え、節約をめざす方法です。
停電時など災害への備えを目的とする場合、電力会社から購入した電気を蓄電池に貯めておき、いざというときに使用します。ただし、蓄電池単体での使用は電力会社からの供給ありきであるため、災害などで電力の供給そのものが停止した場合、新たに蓄電することはできません。
蓄電池をより効率的に活用するには、太陽光発電設備との併用がおすすめです。両者を併用する場合、蓄電池あるいは太陽光発電設備単体では叶えられない「電気をつくって貯める」という環境を実現できます。
蓄電池単体での使用と太陽光発電設備単体での使用、そして2つを併用した場合の違いを下表で確認してみましょう。
このように、蓄電池と太陽光発電設備を併用すれば、自家発電から自家消費までを行えます。電気代が高騰している昨今の状況を考えると、自宅で電気をつくりながら自家消費率を増やすことで、金銭的なメリットを享受しやすくなるでしょう。
なお、2019年よりも前に太陽光発電設備を設置し、なおかつ売電収入を得ている場合には、蓄電池の導入後に売電価格が下がる可能性があります。2018年まで、ダブル発電の売電価格はシングル発電の価格より低く設定されていたためです。
ただし、2019年から、ダブル発電の売電価格はシングル発電と同額になりました。よって、2019年以降に蓄電池を導入した方やこれから新規で設置する方であれば、売電価格の不公平感を心配する必要はありません。
蓄電池にはさまざまな運転モードが備わっており、モードごとに使い方や適した状況が異なります。蓄電池のモードで代表的なものは、以下の3種類です。
※FIT期間中でも、売電単価よりも購入電力単価が高い場合は、環境モードがおすすめです。
モードの名称の詳細はメーカーによって異なるため、蓄電池の取扱説明書などで確認しておくとよいでしょう。各モードの特徴と使い方を順に詳しく解説します。
経済モードは、その名のとおり経済性を最優先して蓄電池を運転します。電気代の節約や売電収入の最大化を目指したい方には、とくに適したモードです。
蓄電池単体で使用する場合と太陽光発電設備と併用する場合で、経済モードの動作には次のような違いがあります。
蓄電池単体の経済モードでは、優先的に電気代の安い時間帯(主に深夜)に電気を電力会社から購入・充電し、昼間にはその貯めた電気を使用するという使い方をします。電気代が高くなりやすい昼間の購入量を減らして、電気代の節約を目的としています。
太陽光発電設備との併用であれば、発電分をできるだけ売電収入へ回したい場合に適したモードです。発電した電気を蓄電池に貯めて自家消費するのではなく、発電分のうち消費しきれない電気をすべて売電にまわすため、売電量を多くすることができます。太陽光発電設備で発電できない時間帯は、蓄電池単体での利用と同様に、電気料金が割安な深夜帯に購入して貯めておいた電気を使用します。
太陽光発電設備と併用し、経済モードに設定した蓄電池は以下のサイクルを日々繰り返します。
ただし、FIT制度の適用期間が終了すると売電価格は大幅に下がるため、収益はあまり期待できなくなります。FIT期間中の売電に特化した使い方といえるでしょう。
※電力会社からの購入金額が、太陽光発電で発電した電気の売電単価より高い場合
環境モードは、太陽光発電設備がつくり出した電気を蓄電池に優先して貯めるモードです。電気の自家消費量を増やすことで、Co2排出量の削減を目指しやすくなります。
環境モードに設定した蓄電池は、以下のような使い方をします。
環境モードで電気の自家消費率を増やすと、電気代の節約につながります。また、FIT期間が終了すると売電価格が下がるため、売電よりも自家消費を増やしたほうが経済的なメリットを期待できるでしょう。
そのため、電気使用量の多いご家庭や、FIT期間の終了後に有効活用しやすい使い方といえます。
蓄電池の安心モードは、停電時に備えて常に一定の電気を貯めておく設定です。災害対策のために蓄電池を導入・導入予定の方に、とくに適した使い方です。
安心モードに設定した蓄電池は、以下のような使い方をします。
このモードでは常に一定の電気が蓄電池に蓄えられるため、突然の停電に備えることができます。
ここまで、蓄電池の基本的な使い方や各モードの特徴を見てきましたが、具体的にどのような基準で製品を選べばよいのでしょうか。日常的な使い方で蓄電池を選ぶ方法、または停電時の使い方で選ぶ方法の大きく2パターンに分けて解説します。
蓄電池にはさまざまな種類が存在し、導入目的に合った製品でなければ思うような効果を得られない可能性もあります。余計なコストを発生させないためにも、日常生活でどのように蓄電池を活用したいのか明確にしたうえで、最適な製品を選びましょう。
日常生活で蓄電池を活用したい場合、電気代の節約が主な導入目的と考えられます。まずは以下の表を基に、蓄電池を設置する目的を整理してみましょう。
日常使いの蓄電池を選ぶ際にチェックしたいポイントは、主に以下の3点です。
各ポイントの検討要素を順に詳しく解説します。
もし蓄電容量が不足していると、「電気の自家消費率を上げたいものの、蓄電容量が小さく売電せざるを得ない」といった状況に陥る可能性があります。これでは、蓄電池の導入目的を達成できない状況にもなりかねません。
家庭用蓄電池の容量選びに不安がある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
家庭用蓄電池の容量選びについて|選ぶ際の注意点も解説>>
太陽光発電設備と蓄電池の併用により、余剰電力を蓄電池に貯め、必要なときに使用できるため、より効率的に自家消費ができます。また、自家消費しきれない分は売電に回せるため、売電収入を得られる可能性があります。
ただし、太陽光発電と蓄電池の併用に対応した製品は、初期費用が高くなりやすいのが懸念点です。製品を選ぶ際は、導入目的だけでなく、予算や将来的な電気の使用計画などを総合的に判断する必要があります。
蓄電池単体の導入では、単機能型となるのが一般的です。ただし、将来的に太陽光発電設備の併用も視野に入れている場合、単機能型では対応できず、結果的に2台のパワーコンディショナーが必要になってしまいます。
蓄電池と太陽光発電設備の同時導入を検討しているのであれば、電気の変換ロスが少ないハイブリッド型を選ぶのも一案です。また、電気自動車を所有しているご家庭や購入を予定している方には、トライブリッド型が便利でしょう。
日常使いを想定した選び方のほか、停電時の備えに重きを置いて蓄電池を選ぶのも一つの手です。停電時に電気が供給される範囲によって、蓄電池は「全負荷型」と「特定負荷型」の2種類に分けられます。
全負荷型は、停電時でも通常時とほぼ変わらない生活を送りたい方に適したタイプです。大型の家電製品にも対応できるものが多く、緊急の際にも住まいの快適性を保ちやすくなります。
対する特定負荷型は、停電時に最低限の電気供給を確保したい場合に適したタイプです。コンパクトなサイズ感で、なおかつ導入価格も比較的抑えやすいため、設置スペースや予算が限られているときの選択肢になります。
なお、どちらの蓄電池でも通常時の電気の供給範囲は同じです。
蓄電池は、目的やご家庭の状況に応じたモードを設定でき、経済モードや環境モード、安心モードなどの使い方次第で、期待できるメリットに違いがあります。また、日常使いに重きを置いて蓄電池を選ぶのか、停電時の備えに重きを置くのかによって、蓄電容量やダブル発電への対応可否、変換方式の見極めも必要です。
蓄電池の導入時には、このようにさまざまな要素を考慮しなければならず、選び方や使い方に迷うこともあるでしょう。
鈴与商事では、豊富な経験と専門知識を活かして、ご家庭の状況やお客様のご希望に合わせた蓄電池・太陽光発電設備をご提案させていただきます。蓄電池の導入をお考えの方、導入済みの蓄電池の運用に不安がある方は、鈴与商事へお気軽にご相談ください。
本記事では、蓄電池の基本的な使い方をはじめ、目的別・モード別の活用方法、最適な蓄電池の選び方までをわかりやすく解説します。蓄電池の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
「導入目的に沿った使い方ができる?」
\蓄電池に関する疑問、お気軽にご相談ください/
\蓄電池に関する疑問、お気軽にご相談ください/
■目次
蓄電池の使い方
操作面での使い方
通常、蓄電池のモードが自動で切り替わることはありません。このため、使用目的や状況に応じて手動でモード変更が必要です。
ただし、停電時には自動で自立運転モードへ切り替わるタイプの蓄電池もあります。自動でない場合、停電時には手動で自立運転モードに切り替えないと、蓄電池から電気を供給できなくなる点に注意しましょう。
すでに蓄電池を導入している、あるいは今後導入を考えているという方は、手動・自動のどちらで自立運転モードに切り替わるタイプなのかを確認しておくと、もしもの停電時にも安心です。
蓄電池の操作方法や機能は、使っている機器の取扱説明書もしくはメーカーの公式ホームページからチェックできます。
目的別の使い方【蓄電池単体の場合】
電気代の節約を目的として日常的に使用する場合、電気代の安い時間帯(主に深夜)に電力会社から電気を購入し、蓄電池に貯めます。蓄電しておいたぶんを電気代の高い時間帯(主に日中)に使うことで、電気の購入費用を抑え、節約をめざす方法です。
停電時など災害への備えを目的とする場合、電力会社から購入した電気を蓄電池に貯めておき、いざというときに使用します。ただし、蓄電池単体での使用は電力会社からの供給ありきであるため、災害などで電力の供給そのものが停止した場合、新たに蓄電することはできません。
目的別の使い方【太陽光発電と併用の場合】
蓄電池単体での使用と太陽光発電設備単体での使用、そして2つを併用した場合の違いを下表で確認してみましょう。
| 使用方法 | 導入設備 | できること |
|---|---|---|
| 単体 | 蓄電池 |
|
| 太陽光発電設備 |
※太陽が出ていて発電できる時間帯に限られる |
|
| 併用 | 蓄電池+太陽光発電設備 |
|
このように、蓄電池と太陽光発電設備を併用すれば、自家発電から自家消費までを行えます。電気代が高騰している昨今の状況を考えると、自宅で電気をつくりながら自家消費率を増やすことで、金銭的なメリットを享受しやすくなるでしょう。
なお、2019年よりも前に太陽光発電設備を設置し、なおかつ売電収入を得ている場合には、蓄電池の導入後に売電価格が下がる可能性があります。2018年まで、ダブル発電の売電価格はシングル発電の価格より低く設定されていたためです。
ただし、2019年から、ダブル発電の売電価格はシングル発電と同額になりました。よって、2019年以降に蓄電池を導入した方やこれから新規で設置する方であれば、売電価格の不公平感を心配する必要はありません。
| <押上効果とは> 蓄電池と太陽光発電設備を併用している家庭で、太陽光による発電・売電をしているあいだに蓄電池の電気も放電し、売電量を増やす効果のことです。売電量が増えることで、収益化を狙いやすくなります。 <ダブル発電とは> 太陽光発電設備でつくり出した電気を売電しているあいだも、蓄電池からの放電を行う発電方法です。つくり出す電気が増えることで、使いきれずに余る電気(余剰電力)も増えるので、蓄電池による押上効果が生まれます。 <シングル発電とは> 太陽光発電設備でつくり出した電気を売電しているあいだは、蓄電池からの放電を停止する発電方法です。売電中は、太陽光発電設備でつくり出した電気を使用して家庭内の使用電力を賄います。 |
蓄電池のモード別の使い方
| 主なモード | 詳細 |
|---|---|
| 経済モード |
|
| 環境モード |
|
| 安心モード |
|
モードの名称の詳細はメーカーによって異なるため、蓄電池の取扱説明書などで確認しておくとよいでしょう。各モードの特徴と使い方を順に詳しく解説します。
経済モード
蓄電池単体で使用する場合と太陽光発電設備と併用する場合で、経済モードの動作には次のような違いがあります。
| 使用方法 | 経済モードの基本動作 |
|---|---|
| 蓄電池単体 |
|
| 太陽光発電設備と併用 |
|
蓄電池単体の経済モードでは、優先的に電気代の安い時間帯(主に深夜)に電気を電力会社から購入・充電し、昼間にはその貯めた電気を使用するという使い方をします。電気代が高くなりやすい昼間の購入量を減らして、電気代の節約を目的としています。
太陽光発電設備との併用であれば、発電分をできるだけ売電収入へ回したい場合に適したモードです。発電した電気を蓄電池に貯めて自家消費するのではなく、発電分のうち消費しきれない電気をすべて売電にまわすため、売電量を多くすることができます。太陽光発電設備で発電できない時間帯は、蓄電池単体での利用と同様に、電気料金が割安な深夜帯に購入して貯めておいた電気を使用します。
太陽光発電設備と併用し、経済モードに設定した蓄電池は以下のサイクルを日々繰り返します。
- 深夜に蓄電池へ電気を100%貯める
- 朝になったら[1]で貯めた電気を使用する
- 昼間は太陽光発電設備で自家発電した電気を使用・売電(蓄電池は待機状態)
- 夕方~夜にかけて[1]で貯めた電気を使用する
- [1]に戻る
ただし、FIT制度の適用期間が終了すると売電価格は大幅に下がるため、収益はあまり期待できなくなります。FIT期間中の売電に特化した使い方といえるでしょう。
※電力会社からの購入金額が、太陽光発電で発電した電気の売電単価より高い場合
環境モード
環境モードに設定した蓄電池は、以下のような使い方をします。
- 昼間は太陽光発電設備によって自家発電した電気を使用する
- 消費しきれない電気は蓄電池に貯める
- 夜間は[2]で貯めておいた電気を使う
- [2]で貯めた電気が足りなくなった場合のみ、電力会社から電気を購入する
環境モードで電気の自家消費率を増やすと、電気代の節約につながります。また、FIT期間が終了すると売電価格が下がるため、売電よりも自家消費を増やしたほうが経済的なメリットを期待できるでしょう。
そのため、電気使用量の多いご家庭や、FIT期間の終了後に有効活用しやすい使い方といえます。
安心モード
安心モードに設定した蓄電池は、以下のような使い方をします。
- 深夜に蓄電池へ電気を100%貯める
- 朝になったら[1]で貯めた電気を使用する
- 昼間は太陽光発電設備で自家発電した電気を使用・売電(蓄電池は待機状態)
- 夕方~夜にかけて[1]で貯めた電気を使用するが、あらかじめ設定した蓄電容量になると放電を停止する
- [1]に戻る
このモードでは常に一定の電気が蓄電池に蓄えられるため、突然の停電に備えることができます。
使い方を踏まえて蓄電池を選びましょう
日常的な使い方で選ぶ
日常生活で蓄電池を活用したい場合、電気代の節約が主な導入目的と考えられます。まずは以下の表を基に、蓄電池を設置する目的を整理してみましょう。
| 導入パターン | 日常使いにおける導入目的の例 |
|---|---|
| 蓄電池単体の導入をお考えの方 |
|
| すでに太陽光発電設備を設置済みの方 |
|
| 蓄電池と太陽光発電設備の同時導入をお考えの方 |
|
日常使いの蓄電池を選ぶ際にチェックしたいポイントは、主に以下の3点です。
- 蓄電容量
- ダブル発電の対応の有無
- 変換方式の種類
各ポイントの検討要素を順に詳しく解説します。
蓄電容量
蓄電容量とは、蓄電池に貯めておける電気の量を意味しており、「kWh(キロワットアワー)」という単位で表されます。製品によって蓄電容量は異なるため、ご家庭の電気の使用状況や太陽光発電設備による発電量を考慮して選ぶことが大切です。もし蓄電容量が不足していると、「電気の自家消費率を上げたいものの、蓄電容量が小さく売電せざるを得ない」といった状況に陥る可能性があります。これでは、蓄電池の導入目的を達成できない状況にもなりかねません。
家庭用蓄電池の容量選びに不安がある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
家庭用蓄電池の容量選びについて|選ぶ際の注意点も解説>>
太陽光発電設備と蓄電池の併用について
太陽光発電設備と蓄電池の併用を考えている場合、両方の機器が正しく連携できるかどうかを確認しておきましょう。太陽光発電設備と蓄電池の併用により、余剰電力を蓄電池に貯め、必要なときに使用できるため、より効率的に自家消費ができます。また、自家消費しきれない分は売電に回せるため、売電収入を得られる可能性があります。
ただし、太陽光発電と蓄電池の併用に対応した製品は、初期費用が高くなりやすいのが懸念点です。製品を選ぶ際は、導入目的だけでなく、予算や将来的な電気の使用計画などを総合的に判断する必要があります。
変換方式の種類
蓄電池に貯めた電気は、パワーコンディショナーという機器を通じて、家庭で使用するための電気に変換されています。その変換方式には、「単機能型」「ハイブリッド型」「トライブリッド型」の大きく3種類があります。| 変換方式の種類 | 詳細・特徴 |
|---|---|
| 単機能型 | 蓄電池専用のパワーコンディショナー
|
| ハイブリッド型 | 「太陽光設備・蓄電池」のパワーコンディショナーが一体化
|
| トライブリッド型 | 「太陽光設備・蓄電池・充電スタンド」のパワーコンディショナーが一体化
|
蓄電池単体の導入では、単機能型となるのが一般的です。ただし、将来的に太陽光発電設備の併用も視野に入れている場合、単機能型では対応できず、結果的に2台のパワーコンディショナーが必要になってしまいます。
蓄電池と太陽光発電設備の同時導入を検討しているのであれば、電気の変換ロスが少ないハイブリッド型を選ぶのも一案です。また、電気自動車を所有しているご家庭や購入を予定している方には、トライブリッド型が便利でしょう。
停電時の使い方で選ぶ
| 停電時の電気供給 | 特徴 |
|---|---|
| 全負荷型 | 停電時:建物全体に電気を供給する
|
| 特定負荷型 | 停電時:事前に決めた範囲にのみ電気を供給する
|
全負荷型は、停電時でも通常時とほぼ変わらない生活を送りたい方に適したタイプです。大型の家電製品にも対応できるものが多く、緊急の際にも住まいの快適性を保ちやすくなります。
対する特定負荷型は、停電時に最低限の電気供給を確保したい場合に適したタイプです。コンパクトなサイズ感で、なおかつ導入価格も比較的抑えやすいため、設置スペースや予算が限られているときの選択肢になります。
なお、どちらの蓄電池でも通常時の電気の供給範囲は同じです。
蓄電池の使い方に関するご相談は鈴与商事へ
蓄電池の導入時には、このようにさまざまな要素を考慮しなければならず、選び方や使い方に迷うこともあるでしょう。
鈴与商事では、豊富な経験と専門知識を活かして、ご家庭の状況やお客様のご希望に合わせた蓄電池・太陽光発電設備をご提案させていただきます。蓄電池の導入をお考えの方、導入済みの蓄電池の運用に不安がある方は、鈴与商事へお気軽にご相談ください。
蓄電池や太陽光発電設備のことなら
\鈴与商事にお任せください/
\鈴与商事にお任せください/