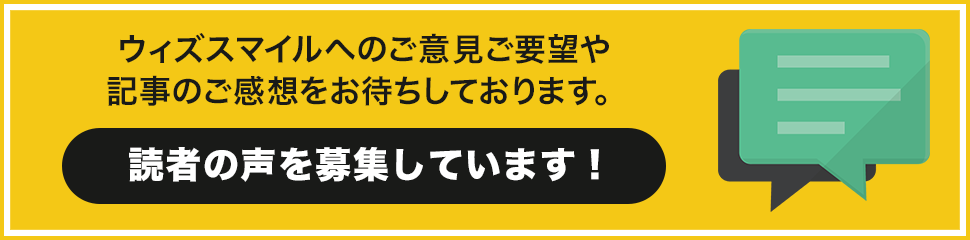くらしの役立ち情報
2017.10.27
意外とカラフル!? カビの種類とその特徴

実は、冬は梅雨と同じくらいカビが発生しやすい時期。その理由は、暖房によって室内外の温度差が大きいこと、洗濯物の部屋干しや加湿器による湿度の上昇などなど。
今回は、色別にみたカビの特徴や対策のポイントをご紹介します。
カビというと湿度の高いところに発生しやすいと考えられがちですが、実はそうでもありません。黄色やオレンジ色をした「カワキコウジカビ」は、湿度が65%以上になると発生すると言われ、比較的乾燥に強い種類のカビです。糖度や塩分が高い食品や穀物のほか、カメラのレンズやフィルムなど、精密機械の基盤に発生することも。
カワキコウジカビは、しょうゆや味噌、鰹節の製造に利用される「コウジカビ」の一種ですが、だからと言って毒性がないわけではありません。「コウジカビ」のなかには強い毒性を持ち、発がん性物質「アフラトキシン」を生成するものもあるので、摂取したり吸い込んだりしないよう注意しましょう。
また、あずき色をした「アズキイロカビ」ものも乾燥を好むタイプのカビです。羊羹やチョコレートなどの甘いお菓子、畳やじゅうたんに発生します。

パンやお餅に発生する、青や緑のカビが「アオカビ」。日常生活の中でもよく見られるタイプのカビで、湿度80%以上になると発生しやすくなります。毒性はそれほど強くなく、間違って摂取しても直接的に健康被害を及ぼすものではないとされていますが、有害な他のカビと合わせて発生すること多いため、やはり摂取はNG。カビが生えている部分を取り除いたからといって食べるのはご法度です。
ブルーチーズの熟成に用いられるのも、このアオカビの仲間。しかし、使われるのは人体に悪影響を及ぼさない食用種のアオカビなので、放置した食物に発生したカビとはまったく別物です。
ちなみに、抗生物質である「ペニシリン」は、アオカビから作られています。

浴槽などに発生するピンク色の汚れ。カビだと思っている方も多いと思いますが、実は酵母菌「ルドトルラ」がその正体なのです。
「ルドトルラ」は増殖スピードが速く、空気中に浮遊する菌が水分の多い場所に付着し3日ほどでピンク色になります。ピンク汚れはこすれば簡単に落ちますが、菌は予想以上にこびりついているため、また3日もすれば繰り返し発生してしまいます。
さらに、ピンク汚れが発生した個所は「これからカビが生えますよ」というサインなので、放置すればそこから黒カビが大量発生することに。そうなる前に、除菌効果のある洗剤や消毒用のエタノールを使って徹底的にピンク汚れを落としておきましょう。

カビと関わることなく暮らしていくには、湿気をためないことと、菌が定着する前に除去することが大切です。こまめなお掃除はもちろんですが、浴槽やエアコンなどカビの生えやすい箇所は、定期的にお掃除のプロにまかしてしまうのも一つの手かもしれませんね。
詳しくはこちらから >>> https://clean.suzuyoshoji.co.jp/
今回は、色別にみたカビの特徴や対策のポイントをご紹介します。
湿度が低くても発生する「黄色いカビ」
カビというと湿度の高いところに発生しやすいと考えられがちですが、実はそうでもありません。黄色やオレンジ色をした「カワキコウジカビ」は、湿度が65%以上になると発生すると言われ、比較的乾燥に強い種類のカビです。糖度や塩分が高い食品や穀物のほか、カメラのレンズやフィルムなど、精密機械の基盤に発生することも。
カワキコウジカビは、しょうゆや味噌、鰹節の製造に利用される「コウジカビ」の一種ですが、だからと言って毒性がないわけではありません。「コウジカビ」のなかには強い毒性を持ち、発がん性物質「アフラトキシン」を生成するものもあるので、摂取したり吸い込んだりしないよう注意しましょう。
また、あずき色をした「アズキイロカビ」ものも乾燥を好むタイプのカビです。羊羹やチョコレートなどの甘いお菓子、畳やじゅうたんに発生します。

青や緑色のカビは取り除けば食べてもOK?
パンやお餅に発生する、青や緑のカビが「アオカビ」。日常生活の中でもよく見られるタイプのカビで、湿度80%以上になると発生しやすくなります。毒性はそれほど強くなく、間違って摂取しても直接的に健康被害を及ぼすものではないとされていますが、有害な他のカビと合わせて発生すること多いため、やはり摂取はNG。カビが生えている部分を取り除いたからといって食べるのはご法度です。
ブルーチーズの熟成に用いられるのも、このアオカビの仲間。しかし、使われるのは人体に悪影響を及ぼさない食用種のアオカビなので、放置した食物に発生したカビとはまったく別物です。
ちなみに、抗生物質である「ペニシリン」は、アオカビから作られています。

ピンク汚れの真実。実はカビじゃない?!
浴槽などに発生するピンク色の汚れ。カビだと思っている方も多いと思いますが、実は酵母菌「ルドトルラ」がその正体なのです。
「ルドトルラ」は増殖スピードが速く、空気中に浮遊する菌が水分の多い場所に付着し3日ほどでピンク色になります。ピンク汚れはこすれば簡単に落ちますが、菌は予想以上にこびりついているため、また3日もすれば繰り返し発生してしまいます。
さらに、ピンク汚れが発生した個所は「これからカビが生えますよ」というサインなので、放置すればそこから黒カビが大量発生することに。そうなる前に、除菌効果のある洗剤や消毒用のエタノールを使って徹底的にピンク汚れを落としておきましょう。

カビと関わることなく暮らしていくには、湿気をためないことと、菌が定着する前に除去することが大切です。こまめなお掃除はもちろんですが、浴槽やエアコンなどカビの生えやすい箇所は、定期的にお掃除のプロにまかしてしまうのも一つの手かもしれませんね。
◆◆◆花粉の前に、お部屋やエアコンの掃除はいかがですか◆◆◆
鈴与商事では、ダスキンのハウスクリーニングを鈴与だけの特典を付けて提供しています。詳しくはこちらから >>> https://clean.suzuyoshoji.co.jp/